5/3/1
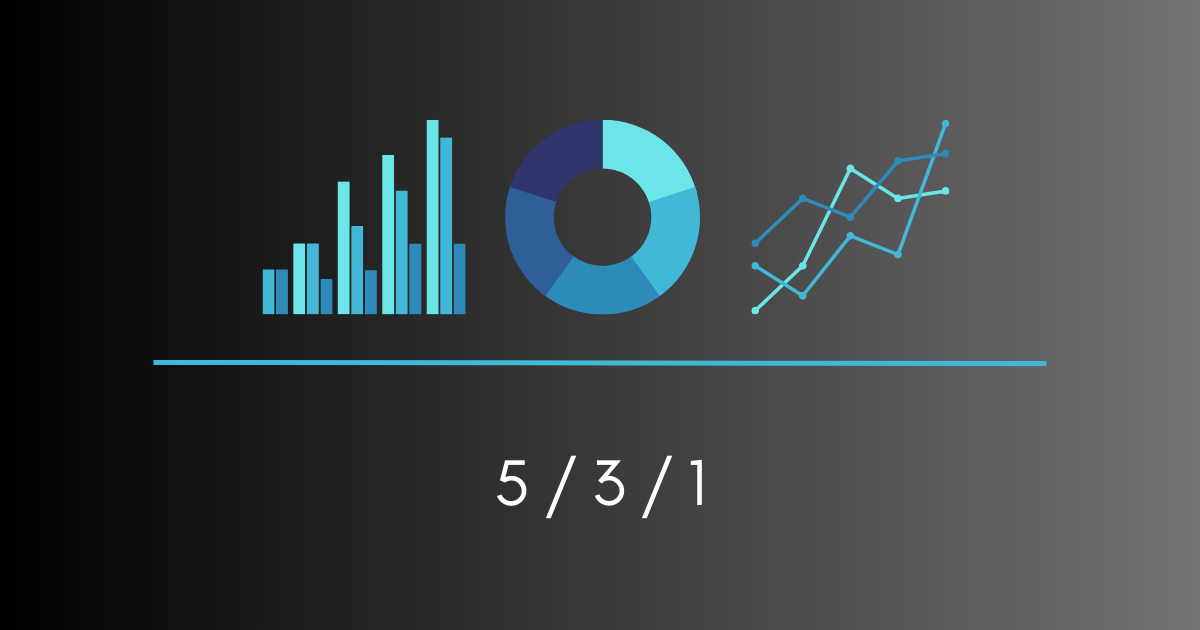
| レベル | プログラム |
|---|---|
| 初心者 | Strong Lifts5×5 Starting Strength |
| 中級者 | テキサスメソッド |
| 上級者 | 5/3/1 スモロフスJr スモロフスクワット ロシアンスクワットルーティーン サイクルトレーニング(中~上級者) |
▼ この記事の内容を動画で解説しています
文章を読む前に全体像を知りたい方は、まずこの動画からご覧ください。
5/3/1基本情報
| 対象レベル | 中~上級者 |
| 対象種目 | 主にBIG3、オーバーヘッドプレス |
| 頻度 | 週4日、1種目週1回 |
| 期間 | 4週 |
5/3/1概要
1週間の流れ
| メイン種目 | 補助種目1 | 補助種目2 | |
|---|---|---|---|
| 1日目 | オーバーヘッドプレス | 種目1 | 種目2 |
| 2日目 | デッドリフト | 種目1 | 種目2 |
| 3日目 | ベンチプレス | 種目1 | 種目2 |
| 4日目 | スクワット | 種目1 | 種目2 |
※補助種目のバリエーションは様々
1サイクル(4週)の流れ、重量・回数・セット設定
| 週 | セット1 | セット2 | セット3 |
|---|---|---|---|
| ① 5/5/5 | 65%TM×5 | 75%TM×5 | 85%TM×5+ |
| ② 3/3/3 | 70%TM×3 | 80%TM×3 | 90%TM×3+ |
| ③ 5/3/1 | 75%TM×5 | 85%TM×3 | 95%TM×1+ |
| ④ deload | 40%TM×5 | 50%TM×5 | 60%TM×5 |
※TM:トレーニングマックス(90%1RM)
※+(AMRAP):余裕があればRPE8〜9程度まで回数を追加して行う
※deload:負荷を下げて疲労を抜く
※deloadの頻度:余裕があれば1~3週を2サイクル行ってから取り入れる
5/3/1計算機
こちらのサイトで使用重量を一括計算できます。
🧮 1RM計算機を使用する
使い方・解説
✅ 使い方
- トレーニングで使った「重量(kg)」を入力します
- その重量で「何回(reps)挙げたか」を選択します
- 「種目(ベンチプレス/スクワット・デッドリフト)」を選びます
- 「計算する」ボタンを押すと、1RM〜10RMまでの推定重量が表示されます
🏋️♂️ RM計算機について
このRM計算機では、「ある重量で何回持ち上げたか」をもとに、あなたの推定1RM(1回だけ挙げられる最大重量)を算出します。
さらに、1RMをもとに2RM〜10RMまでの目安重量も一覧で確認できます。
🔍 RMとは?
RM(Repetition Maximum)は、「その重さで何回できるか」を示す指標です。
| RM | 意味 |
|---|---|
| 1RM | 1回だけ挙げられる最大重量 |
| 5RM | 5回がギリギリできる重量 |
| 10RM | 10回が限界の重量 |
RMを知ることで、目的に応じたトレーニング強度を設定しやすくなります。
⚠️ 注意事項
- あくまで推定値であり、実際の最大挙上重量とは異なる場合があります
- 正確な数値を知りたい場合は、安全に配慮したうえで実測をおすすめします
- 体調や疲労によって結果が前後することもあります。目安としてご活用ください
RMについてより詳しい解説が必要な場合は以下の記事を参考にして見てください。

🧮 RPE計算機を使用する
使い方・解説
✅ 使い方
- トレーニングで使った「重量(kg)」を入力します
- その重量で「何回(reps)挙げたか」を選択します
- 体感のきつさに応じた「RPE」を選びます
- 「計算」ボタンを押すと、推定1RMとRPE別の重量が表示されます
- 表のタブを切り替えると、他の回数でのRPEチャートも確認できます
🏋️♂️ RPE計算機について
このRPE計算機では、「何kgで何回・どれくらいのきつさ(RPE)で持ち上げたか」をもとに、あなたの推定1RM(1回だけ挙げられる最大重量)を計算できます。また、そこからRPEごとのトレーニング重量の目安も一覧で確認できます。
🔍 RPEとは?
RPE(Rate of Perceived Exertion)は、「あと何回できそうか?」を基準にした自覚的なきつさの指標です。
| RPE | 意味 |
|---|---|
| 10 | 限界、これ以上は無理 |
| 9 | もう1回できたかもしれない |
| 8 | あと2回できたかもしれない |
| 7 | まだ余裕がある |
⚠️ 注意事項
- あくまで推定値であり、実際の最大挙上重量とは異なる場合があります
- RPEの感覚は個人差があります。無理をせず、安全を最優先してください
- 小数点以下は2.5kg単位で丸めて表示しています
- 体調や疲労度によってもRPEの感じ方は変わります。目安として活用してください
トレーニングの記録やメニューの調整にぜひご活用ください!
RPEについてより詳細に知りたい方は以下の記事も参考にして見てください。

5/3/1のおすすめポイント
設定が毎回変わり飽きない
5/3/1は1サイクルを通して毎回重量・回数設定が変わるため、マンネリ化しにくく飽きにくい構成になっています。
毎回フレッシュな気分で臨めるでしょう。
調子が良ければ一気に回数を増やせる
5/3/1は最後の3セット目は+が付いています。
これは、余裕があったら予定回数を超えて行うことを意味しています。※フォームが崩れない範囲で
このため、調子が良ければ一気に回数ベストを大幅に更新することが可能です。
様々な回数のMAXを伸ばせる
5/3/1はその名の通り、5回、3回、1回の3種類の回数設定となっています。
そのため、5RM、3RM、1RMの3種類のMAX更新を目指すことができるようになっています。
1RMの更新が難しくても3RMや5RMが伸びることは多々あるため、どこかしらで成長を感じることができます。
deloadが組み込まれている
deloadの目的は、敢えて一時的に使用重量を落とすことで、疲労の回復を図ることです。
これが3週間おきに組み込まれているので、疲労が溜まり過ぎることを予防できます。
ちなみに余裕がある場合は無理にdeloadを行わず、直ぐに次のサイクルに突入しても構わないとされています。
繰り返しサイクルを行える
5/3/1は重量設定も毎回変わるしdeloadもあります。
そのためマンネリ化しにくく、疲労も管理しやすいため、何サイクルも続けて行うことができます。
補助種目のバリエーションが豊富
5/3/1はかなりバリエーションが豊富なプログラムです。
特に補助種目のバリエーションが豊富で、色々な方法があります。
バーベルを使用した種目だけでなく、ダンベルやマシン、自重など自分の弱点に合わせて様々な方法を採用可能です。
また補助種目としてメイン種目を重量を下げて行うことでボリュームを増やすという方法もあります。
このようにバリエーションが非常に豊富でプログラムの柔軟性が高いのでカスタマイズ性が高くなっています。
5/3/1のデメリット
BIG3の頻度が少ない
5/3/1はBIG3の頻度が週1回ずつと非常に少な苦なっています。
デッドリフトであれば週1回でも良いかもしれませんが、スクワット・ベンチプレスが週1回というのはとても少ないです。
ここ最近の動向では、ベンチはエブリに近い高頻度で記録を伸ばす選手が多いし、スクワットも高頻度で回す選手が多いように感じるので頻度の少なさは少し気になるところです。
パワーリフティング目線で見た5/3/1
BIG3の練習頻度が少なすぎる
デメリットでも述べた通りBIG3の頻度・ボリュームがとても少なくなっています。
BIG3を各週1日ずつというのはパワーリフティングの練習としては非常に少なく成長には効率が悪いかもしれません。
パワーリフティング用として採用するならアレンジバージョンあり
5/3/1は様々なバリエーションや応用方法が紹介されており、パワーリフティング用のプログラムとして採用するのであれば参考にすることをおすすめします。
5/3/1まとめ
「5/3/1」は…
- マンネリ化しにくく飽きない
- 色々なレップ数のMAX更新を狙える
- バリエーション豊富

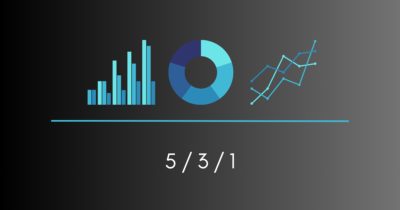
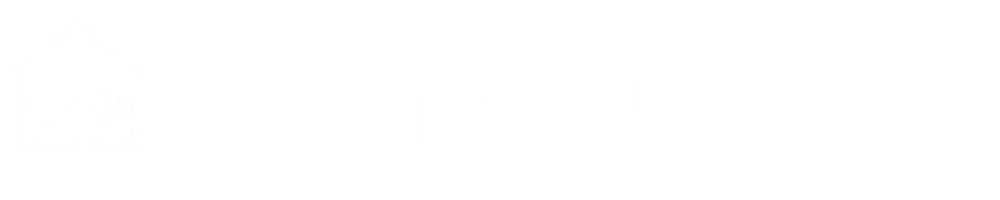
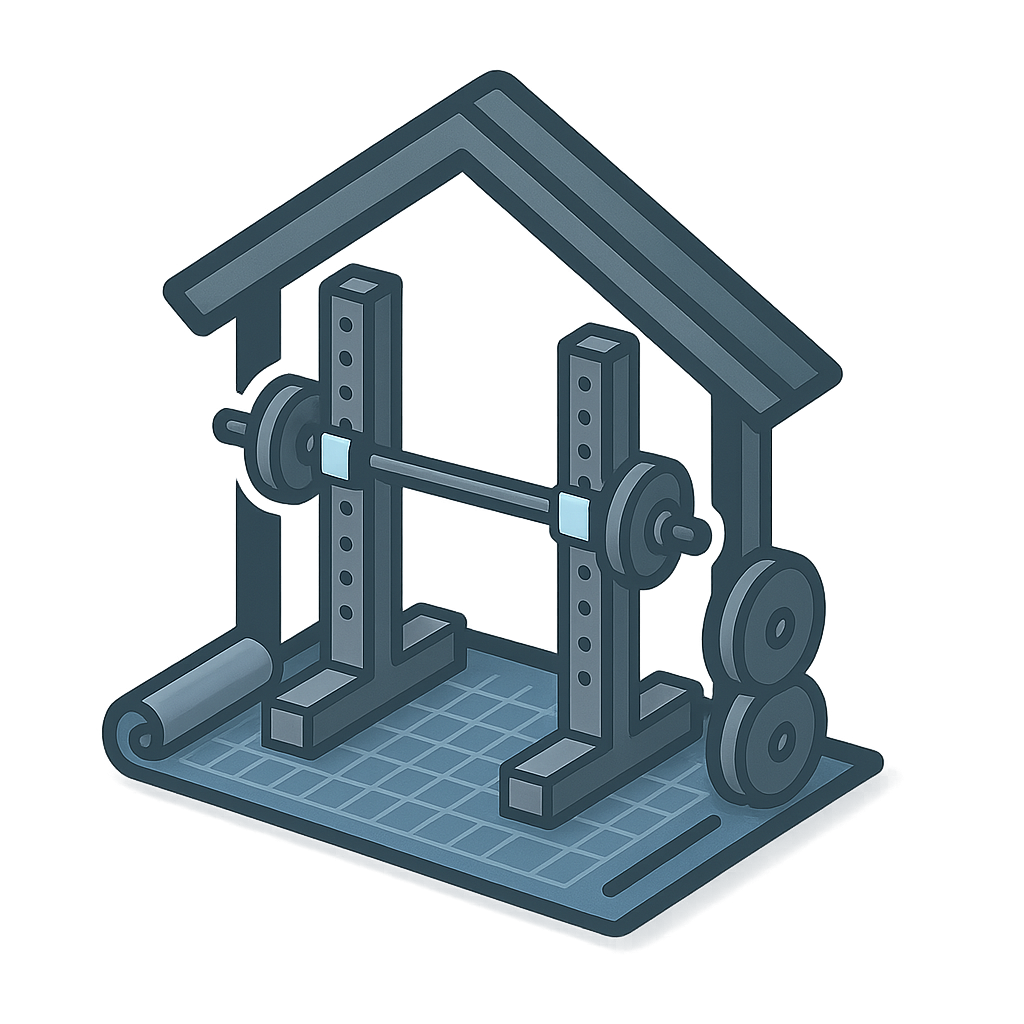


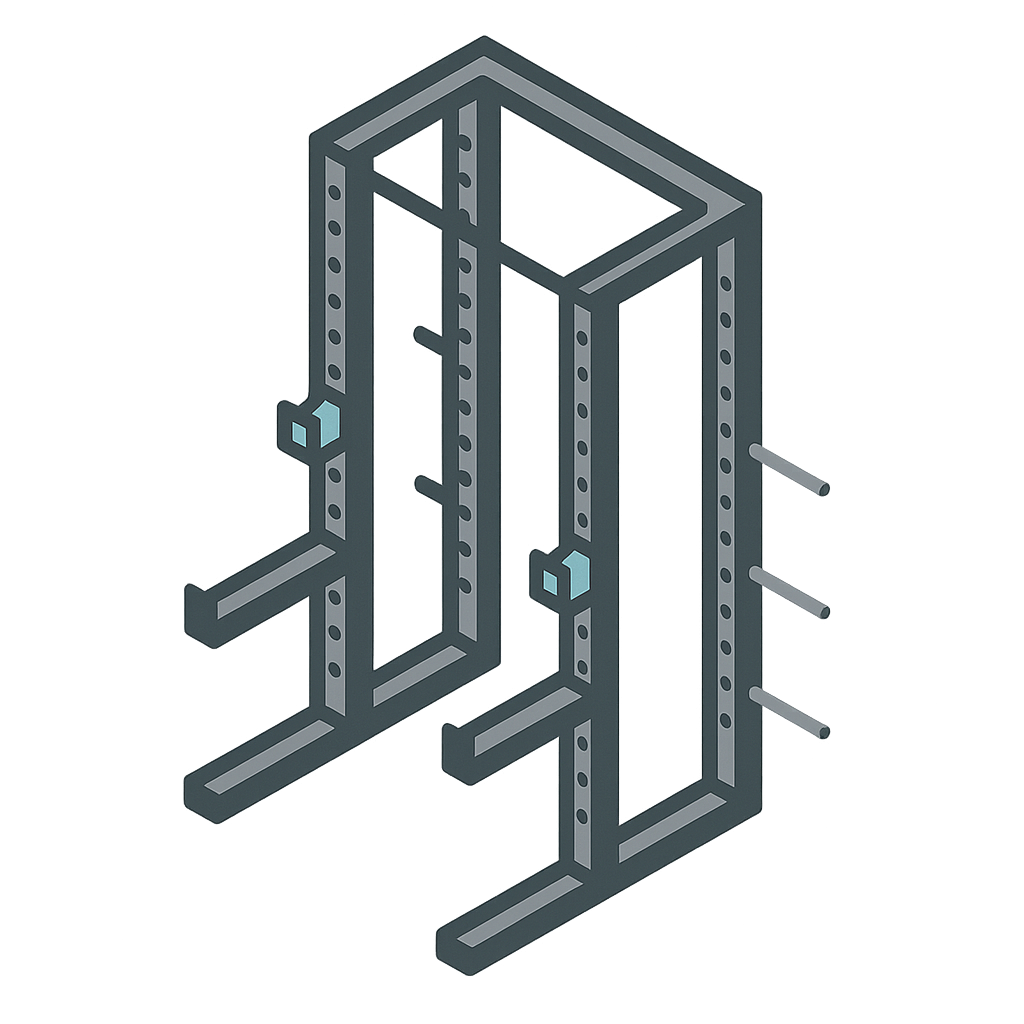
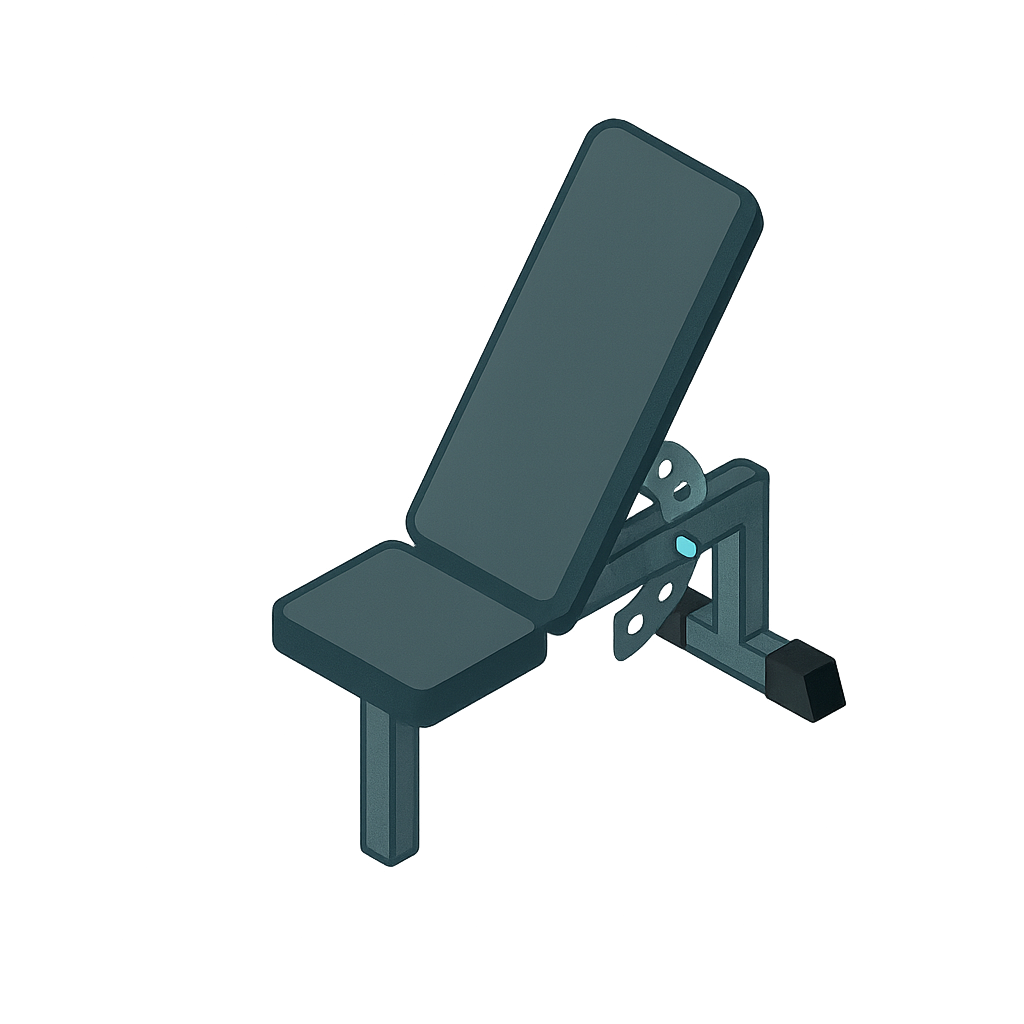
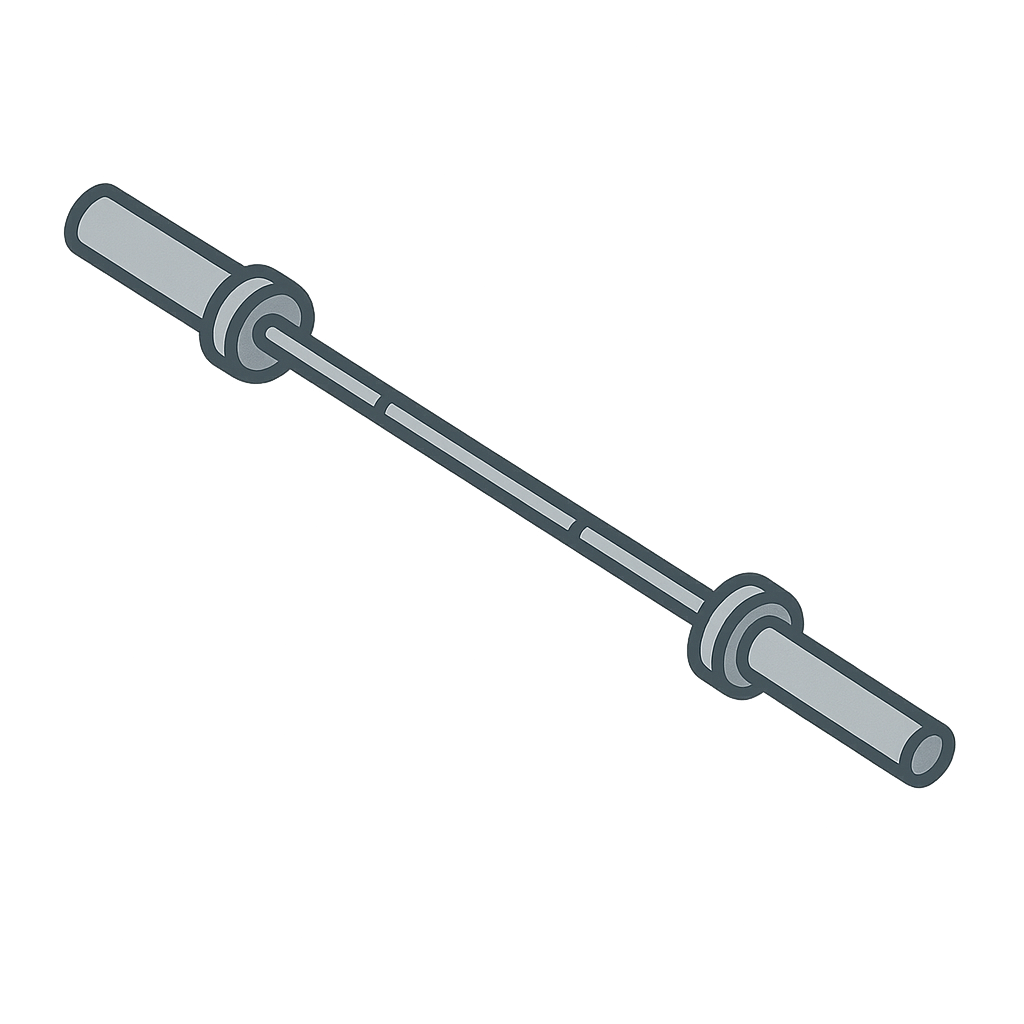
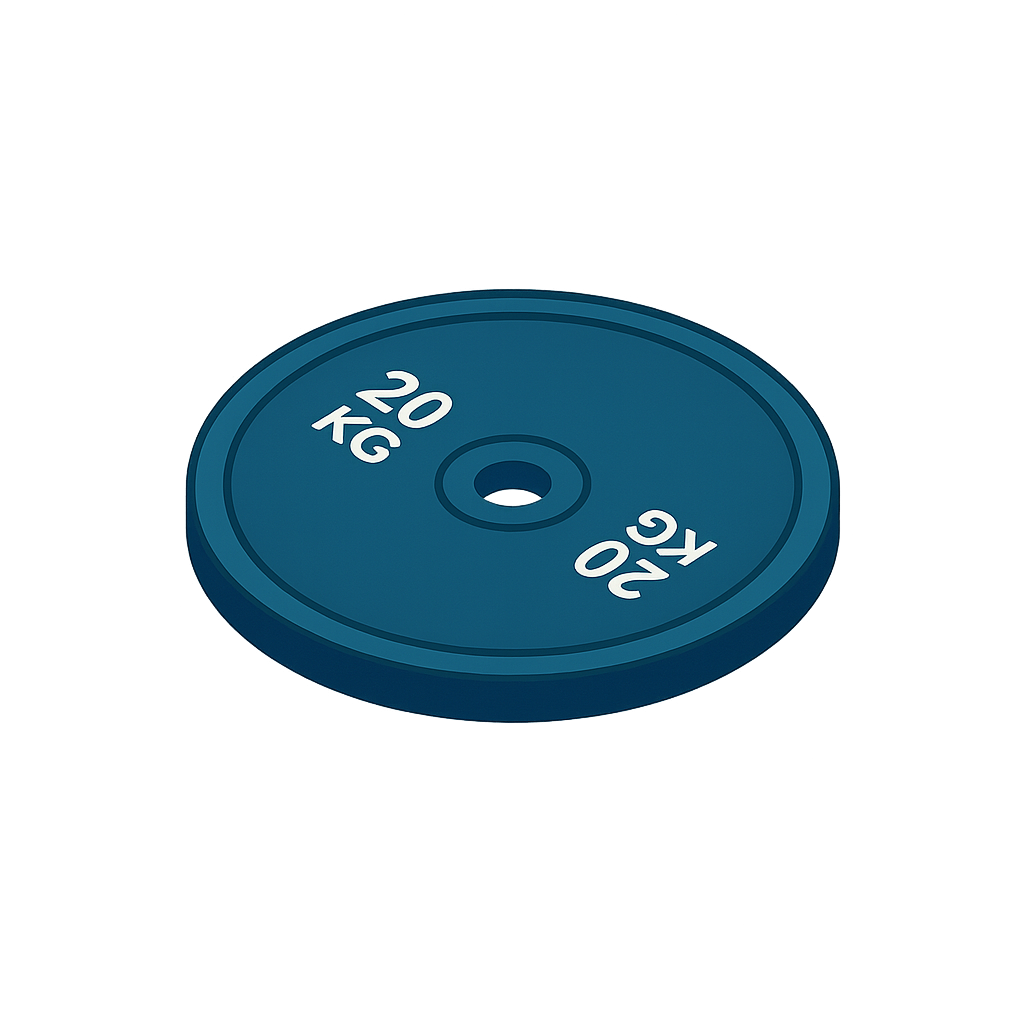
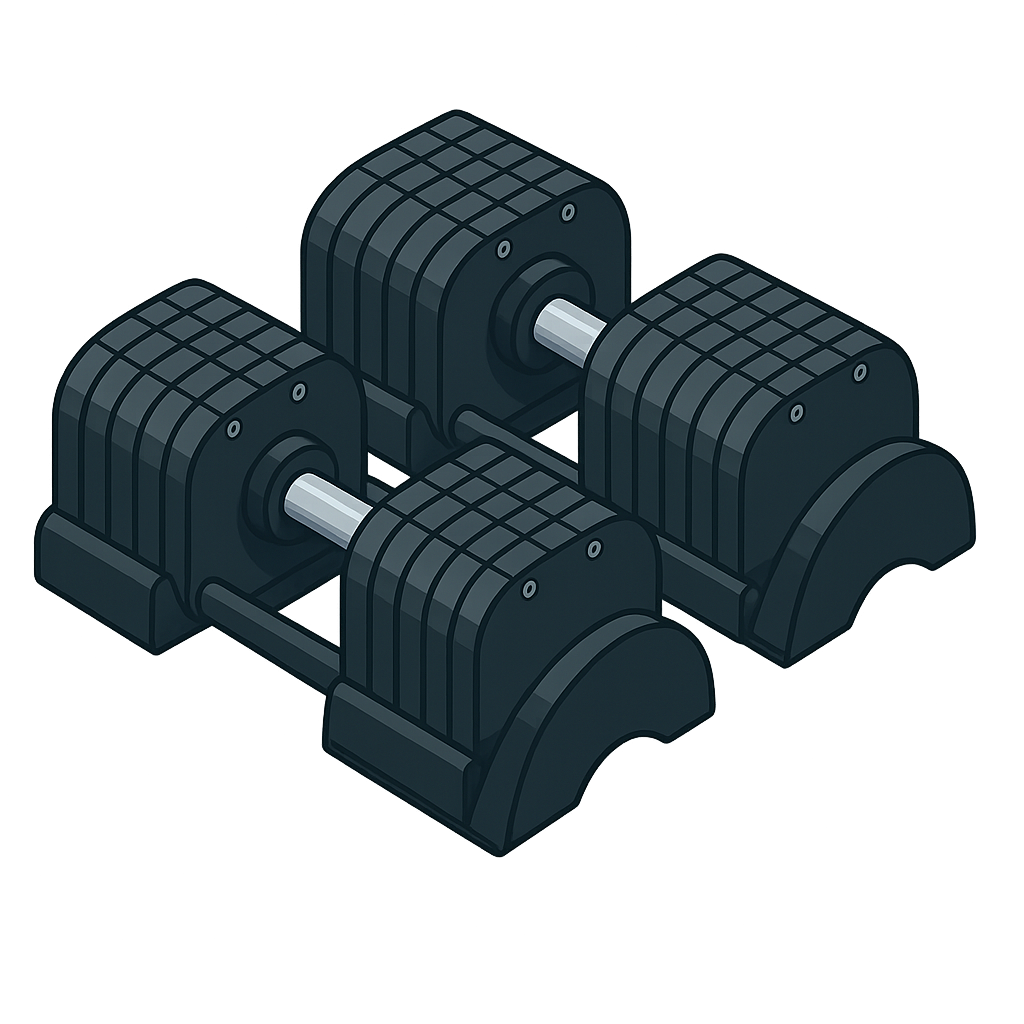







コメント