RPE推定ツール
RPE推定ツール
基本設定
※ RIRは「あと何回できそうか」。未入力でもOKです。
ラスト1repの体感
セット内速度低下(主観)
フォームエラー(複数選択可)
疲労感(複数選択可)
スティッキングポイント
判定結果
RPE8.0
要点
- RPEは「1つの感覚」で決めるとブレる。
- 本ツールは 複数の観点(ラスト1rep体感/セット内速度低下/フォームエラー/スティッキング/疲労感/任意RIR) を合成して判定。
- 種目(BIG3/コンパウンド/アイソレート)×レップ帯(低/中/高) に応じて重みも変える。
- 出力は0.5刻み。軽すぎる領域は 「RPE ≤6」 と表示(内部は5.0まで許容)。
- あくまで 目安。最終判断はご自身の動画・記録と合わせて微調整する。
目次
なぜこのツールが必要だったのか
昨今のトレーニングプログラムはRPEを使用しているものが多くなっています。
トップ選手を真似してRPEを使用したプログラムを実践する人も多いでしょう。
しかし慣れていないとRPEを正しく判定するのは難しいです。
間違った判定をすると本来のプログラムの意図から外れ、破綻してしまうことも珍しくありません。
単一指標の“落とし穴”
一般的にRPEはRIRのように「あと何回できるか?」を目安に考えるよう説明されることが多いです。しかし実際にはそれがかなり難しく、シーンによってはそれ以外の要素を考えた方がいいかもしれません。
- RIRだけ:高レップやパンプが強い場面で急に当てにならない。またMAXに近い重量帯ではどの重量もRPE9.5とかになってしまう。
- 速度だけ:ベンチは軽くても速く見えやすく、デッドは成功レップでも遅い。種目特性が強く乗る。また速度を出さずにゆったりしたリズムでやる人もいる。速度を意識し過ぎるのはフォームエラーにつながる可能性がある。
- 主観だけ:緊張・恐怖・痛み・睡眠不足などで簡単にバイアス。
じゃあどうする?
現場で安定して判断するには、互いの欠点を打ち消す複数の観点を“ほどよく足し合わせる”のが合理的だと考えました。
このツールは、以下の情報源を状況に応じて重み付けして合成します。
- ラスト1repの体感(速い/普通/粘る/止まりかけ)
- セット内速度低下(主観)(<15% / 15–30% / 30–45% / >45%)
- フォームエラー(複数選択可)(再現性の崩れ・安定性の低下)
- スティッキングポイント(なし/わずか/明確/失敗)
- 疲労感(複数選択可)(局所バーン/パンプ、強い息切れ、体幹のブレ)
- 任意の自己申告RIR(未入力でもOK。入力時は最終値を“穏やかに”補正)
RPE評価が難しい「具体的な場面」
レップ帯で変わる“正解の見つけ方”
- 低レップ(1–3)
- 成功レップでも動画はゆっくり見えやすい。
- スティッキングの有無、ラスト1rep体感、フォームの再現性を最優先。
- 中レップ(4–8)
- 神経疲労と代謝負荷のバランス帯。
- 体感+停滞にフォームの崩れが加わると一気にRPE上昇。
- 高レップ(9–12)
- パンプ・呼吸・集中力低下が支配的。速度より疲労感の重みを上げる。
種目特性のクセ
- スクワット:姿勢・可動域の変化(浅くなる/前傾増)が体感に直結。
- ベンチ:見かけ上は速い。胸上ストールや軌道乱れが強いシグナル。
- デッド:基本遅い。速度よりバー距離・背中の張り・膝上ストールを重視。
※ストール:バーや動きが途中で「止まりかける/止まる/ものすごく遅くなる」状態
コツ:速度は“補助輪”。停滞・フォーム再現性を先に見て、足りない分を速度やRIRで埋める。
ツールの仕様と判定思想
入力内容
- 種目(BIG3/コンパウンド/アイソレート)
- レップ帯(低/中/高)
- 任意:自己申告RIR(未入力OK)
- ラスト1repの体感
- セット内速度低下(主観)
- フォームエラー(複数選択可)
- スティッキングポイント
- 疲労感(複数選択可)
どう合成される?
- コア信号(ラスト1rep体感/スティッキング/フォームエラー)
- 補助信号(セット内速度低下/疲労感/RIR)
- 重みはコンテキストで変化:
- 低〜中レップ:コア信号寄り
- 高レップ:疲労感の寄与↑
- BIG3:フォームエラー+停滞を厳しめ
- アイソレート:疲労感寄り
- 出力:0.5刻み。軽すぎる場合は RPE ≤6(内部は5.0まで)。
FAQ
免責と前提
- 本ツールは参考情報です。
- 体格・可動域・経験年数・その日の体調で個人差があります。
まとめ
- 単一指標に頼らないことが、RPE判定の安定化の鍵。
- 種目・レップ帯に応じて何を重視するかを変える。
- ツールで“型”を作り、動画+個人補正で微調整していく。

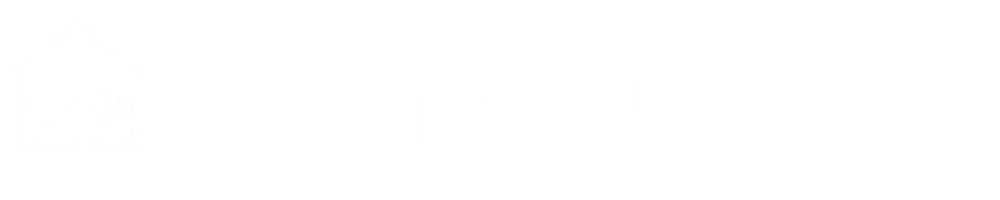
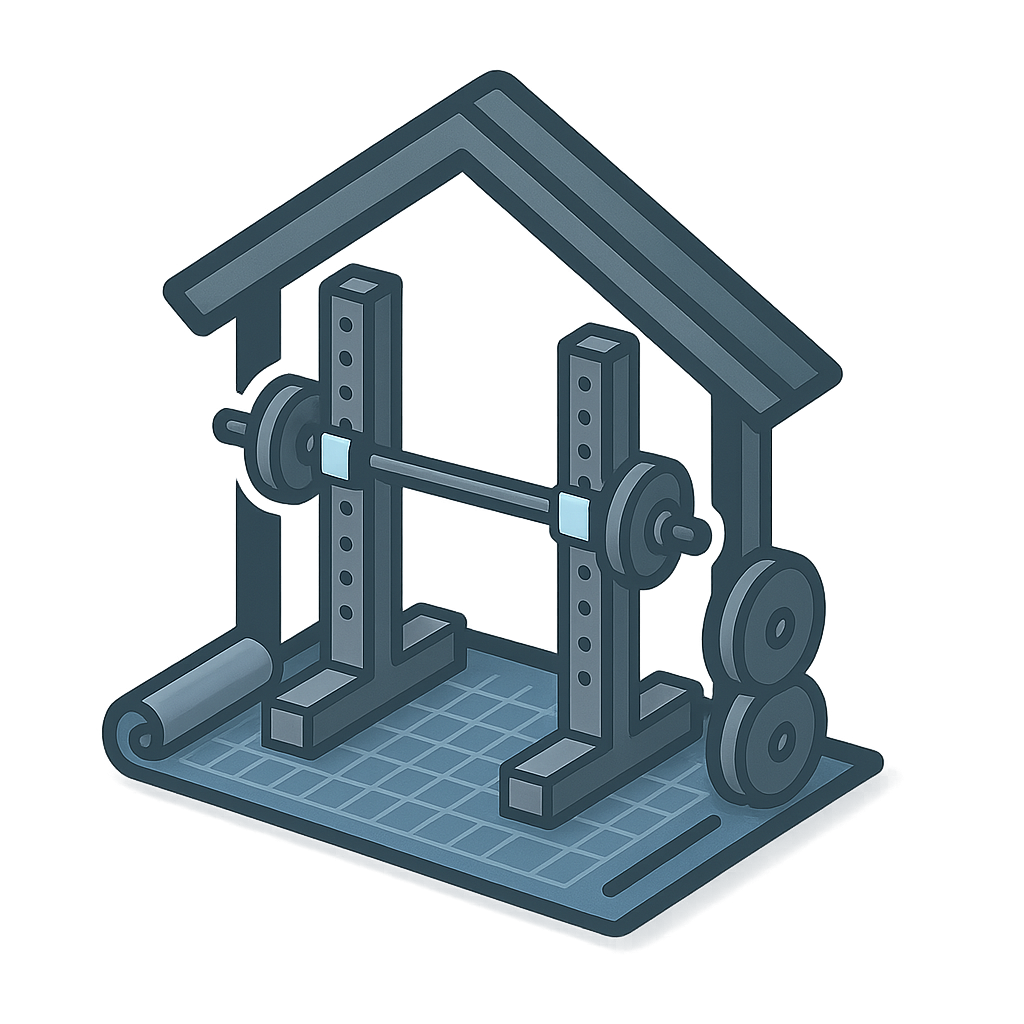


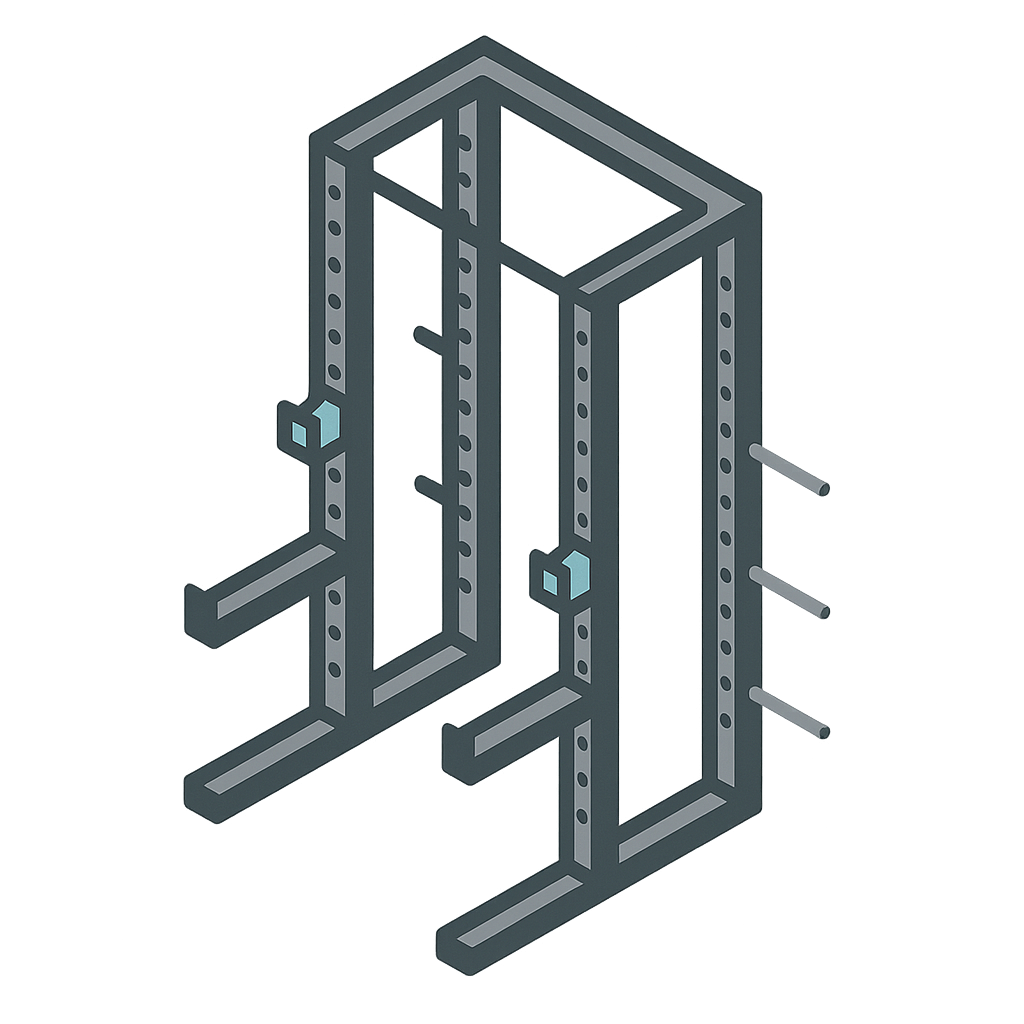
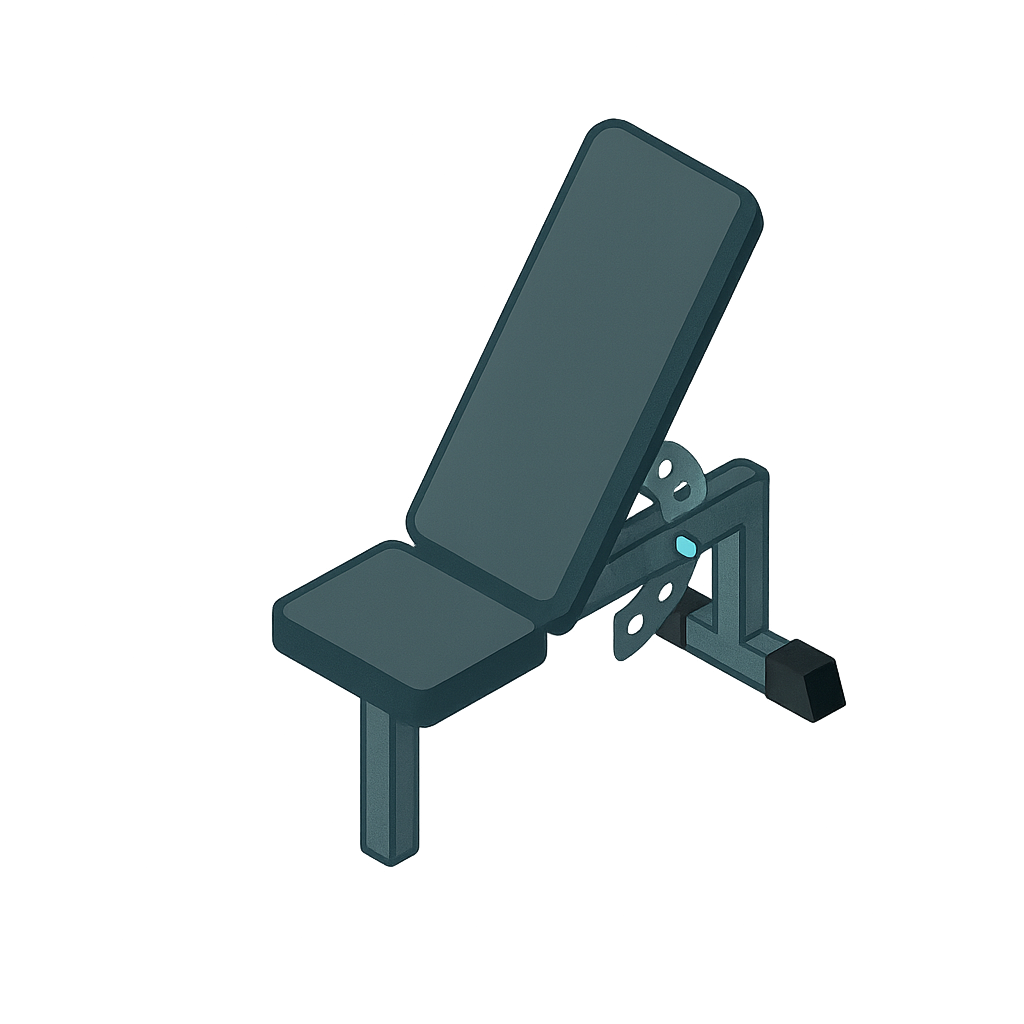
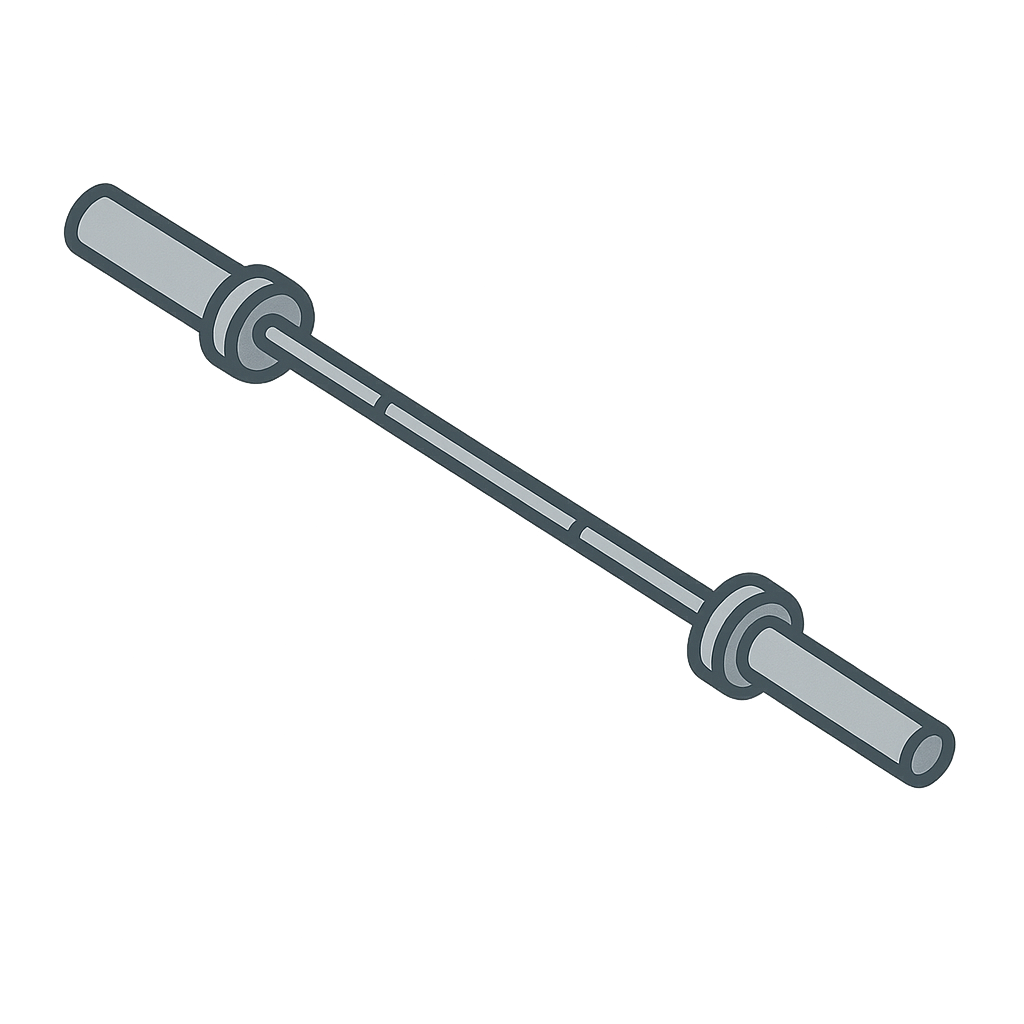
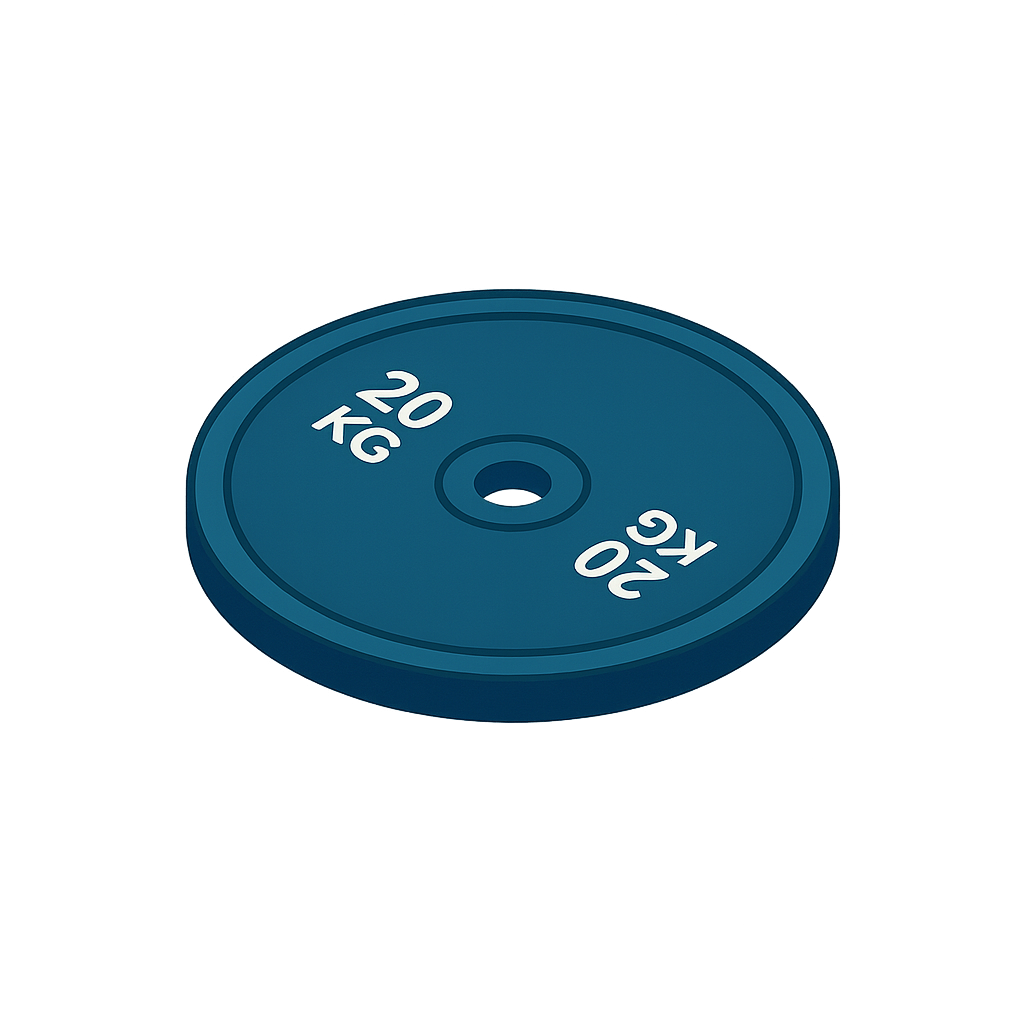
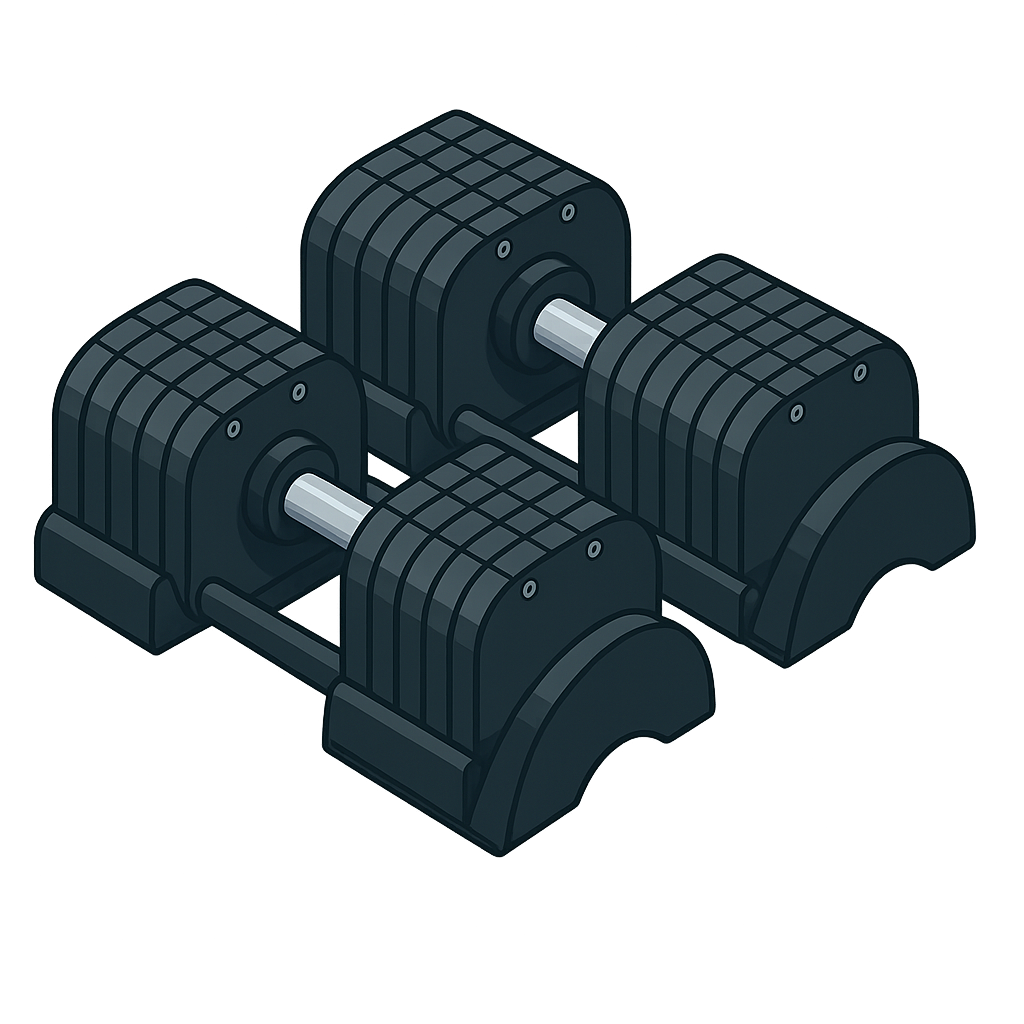






コメント