リフティングシューズ【効果・種類・使用方法・選び方・おすすめ商品】

こちらのツールでご自身に合うリフティングシューズの大まかな推奨スペックが分かります。
その後比較ツールで推奨スペックに合うシューズを探して見てください。
より詳細なリフティングシューズの考え方や選び方などが知りたい方はその後に続く記事をご覧ください。
リフティングシューズ診断
⚠️ 本ツールはトレーニングシューズ選びの目安です。最終的には必ず実物で試着し、動いてみて合う・合わないを確認してください。
各項目の目安
壁つま先テスト(足首の可動域)
- やり方
つま先を壁から5〜12cm離して置き、かかとを浮かせずに膝を曲げて前へ出し膝が壁に触れる最大距離を測ります。左右それぞれ、立位で実施。1〜2回の予備運動後に測ると安定します。 - 目安
〜6cm:足首はやや硬め →「高めヒール寄り」が効きやすい
7〜9cm:平均 →「標準ヒール」基準
10cm〜:余裕あり →「低め〜標準」で比較 - 迷ったら:8〜9cm相当で入れておけば標準判定に近づきます。
主な目的(競技・用途)
- ウェイトリフティング:スナッチ/クリーン&ジャークをよく行う方。
- パワーリフティング:スクワットの記録向上が主目的の方。
- 一般トレーニング:フロントSQやOH種目も混ぜる、幅広く鍛える方。
- 迷ったら:「一般トレーニング」にしておけば無難です。
【スクワット担ぎ(バー位置)】
- ハイバー寄り:首の付け根に近い上背に担ぐ/上体を立てたい。
- 中間:その中間。フォームや日によって担ぐ位置がブレる方。
- ローバー寄り:僧帽筋下部〜三角筋後部に担ぐ/前傾がやや増える。
- 迷ったら:今、動画を撮ると一目です。判断しづらい時は「中間」。
スクワットのスタンス
- ナロー:肩幅以下〜肩幅くらい/つま先0〜15°。膝主導が多め。
- ミドル:肩幅前後/つま先15〜30°。最も汎用的。
- ワイド:肩幅+半足幅以上/つま先30〜45°。股関節主導が多め。
- 迷ったら:「ミドル」にして、つま先角度は5°ずつ見直すのが近道です。
足の横幅(ワイズ)
- 細め:普段から細めのシューズを選ぶ/靴内で横に泳ぎやすく、踏み込みで小指側の内側壁に擦れやすい。
- ふつう:多くのシューズで違和感が出にくい。
- 幅広:多くのシューズで小指側が圧迫されやすい/羽根(紐の両側)が広く開く。
- 迷ったら:「ふつう」→試着で小指側の当たりをチェックしてください。
甲の高さ(ボリューム)
- 甲低め:多くのシューズできつく締めても甲上に隙間が残る/踵が浮きやすい。
- 甲ふつう:多くのシューズで締めればぴったり、痛みも出にくい。
- 甲高め:多くのシューズで甲が痛い・しびれる/羽根が最初から大きく開く。
- 迷ったら:「甲ふつう」→甲中央2〜3列の紐を1段だけ緩めて感覚を確認。
足のアーチ(当たりの敏感さ)
- 気にならない:標準的なインソールでOK。
- 当たりが気になる:土踏まずの“盛り”が合わない体質/面で支えるタイプや低めのアーチが快適なことが多い。
- 迷ったら:「気にならない」にしておき、気になる場合のみ切り替えます。
【床のタイプ】
- 木床/プラットフォーム:競技台・木目の床。グリップ安定。
- ラバー床(一般的ジム):床材との相性差が出る。粉体で滑りやすいなら溝やサイピング多めが有利。
- 迷ったら:通っているジムの床材に合わせて選んでください。
比較ツール
以下のツールで比較したいリフティングシューズを選択することで、スペックを比較できます。
※正確なスペックは公式サイトや各ECサイトをご確認ください。
選択してください
| NOTORIOUS LIFT 「ローニンリフターズ」 |
|---|
 |
| タイプ スクワットシューズ |
| 価格 24,600 円 |
カラーバリエーション   ブラック/ゴールド ステルス ブリスホワイト |
| ヒール高 20 mm |
足型の特徴 ワイドトゥボックス |
| ヒール素材 表記なし |
| アッパー素材 通気性のあるメッシュ |
アウトソール ラバー (Novus 2.0™ Griptech) |
| インソール 非圧縮性インソールでエネルギーロスを軽減 アーチサポート:ニュートラル |
| ストラップ デュアルストラップ |
| ループ なし |
| 特徴 20mmのヒール・トゥ・ドロップ ワイドトウボックス Novus 2.0™ Griptech 非圧縮インソール 広めのソールベース 強化されたヒールカウンター 通気性のあるメッシュアッパー |
| MBC POWER SHOP |
| – |
選択してください
| NOTORIOUS LIFT 「ローニンリフターズ」 |
|---|
 |
| タイプ スクワットシューズ |
| 価格 24,600 円 |
カラーバリエーション   ブラック/ゴールド ステルス ブリスホワイト |
| ヒール高 20 mm |
足型の特徴 ワイドトゥボックス |
| ヒール素材 表記なし |
| アッパー素材 通気性のあるメッシュ |
アウトソール ラバー (Novus 2.0™ Griptech) |
| インソール 非圧縮性インソールでエネルギーロスを軽減 アーチサポート:ニュートラル |
| ストラップ デュアルストラップ |
| ループ なし |
| 特徴 20mmのヒール・トゥ・ドロップ ワイドトウボックス Novus 2.0™ Griptech 非圧縮インソール 広めのソールベース 強化されたヒールカウンター 通気性のあるメッシュアッパー |
| MBC POWER SHOP |
| – |
はじめに
リフティングシューズは、スクワットやフロントスクワット、オーバーヘッド系の動作で姿勢を整え、安定して力を出すためのヒールが高くなった専門シューズです。
リフティングシューズにはウェイトリフティングシューズとスクワットシューズがあります。
ウェイトリフティングシューズはダイナミックな動きを必要とする分、スクワットシューズと比較しやや柔軟性が高く作られています。
この記事のゴールは、「自分に合う一足を理屈から選べる」ようになることです。
なぜなら足首の柔軟性やフォーム、足の形は人それぞれです。
だからこそ「人気」「価格」「見た目」よりも、自分の足型・柔軟性・フォームとの相性が最優先になります。
この記事では、以下の順で解説していきます。
リフティングシューズの基本
何が変わる?
- かかとを約15〜25mm“かさ上げ”
→ 足首の背屈不足を補い、深くしゃがみやすくなる - つぶれにくい靴底
→ 力が床からバーへまっすぐ伝わりやすい - 横方向のブレを抑制
→ 膝が内側に入りにくい
スクワットで深さや上体角度を決める要は足首の背屈です。
ヒールが高いと、すねを前に倒しやすくなり、股関節・体幹の角度にも余裕が生まれます。
さらに靴底が硬いと、沈み込みが減り、踏んだ力が床からバー(シャフト)へまっすぐ伝わりやすくなります。
横剛性が高いことも、重さで足が内外に倒れるのを防いでくれます。
向き・不向き
- 向いている種目:スクワット、フロントスクワット、オーバーヘッドスクワットなど
- 不向きな種目:デッドリフト
スクワット系はヒールの恩恵が大きく、特にフロント系や頭上に保持する動きで重宝します。
一方デッドリフトは「バーを持ち上げる距離」を短くでき、床反力を感じやすい薄底が有利なことが多いです。
自己診断(あなたの“型”を決める)
ステップ1:足首の柔らかさ(壁つま先テスト)
壁つま先テスト(Knee-to-Wall/Weight-Bearing Lunge Test)
- 壁から5〜12cmの位置に、計測する足のつま先を置く(かかとは床に付けたまま)
- 膝を第2趾方向にまっすぐ出し、かかとを浮かせず触れられる最大距離を記録(左右2〜3回)
距離の目安
- 〜6cm
→背屈がやや不足 → 高めヒール(例:25mm級)も候補に入れる - 7〜9cm
→平均的 → 標準ヒール(20〜22mm)から合わせていく - 10cm〜
- →柔らかめ → 低め(15〜16mm)〜標準で比較
このテストは、しゃがむ時に必要な“足首の前方向への倒れ(背屈)”の余裕を簡単に数値化するチェックです。
距離が短いほどしゃがみ込みでかかとが浮きやすくなり、上体が過度に前傾しやすくなるため、ヒールで足首の不足分を“かさ上げ”すると姿勢づくりが楽になります。
なお、体格差(下腿の長さ等)が距離に与える影響は小さめですが、厳密な比較をしたい場合は、スマホの傾斜計などで脛の前傾角(度)も併記すると安心です。
ステップ2:スクワットのフォーム(バー位置 × スタンス)
- ハイバー×ナロー寄り
→上体を立てやすくするため、標準〜高めヒールが合いやすい。 - ローバー×ワイド寄り
→股関節主導で重心が低く安定しやすいので、低めヒール〜フラットも有力。
ハイバーは膝関節の関与が増え、上体を立てたまま重心を保ちたいスタイルです。ここにヒールの補助が加わると、深さと姿勢が両立しやすくなります。
一方ローバー×ワイドは股関節優位で、足関節に求められる背屈可動域小さいため、低め〜フラットの方が据わりが良くなるケースが多いです。
ステップ3:足の形(足幅/甲高/土踏まず)
- 幅広・甲高
→ワイドめのトゥボックス+調整幅の大きいストラップ(2本など)が安心 - ナロー・甲低
→踵カップのホールド感と甲周りの密着感を重視 - 土踏まずが敏感
→アーチサポートの当たり(インソール形状)が合うモデルを優先
大切なのは「履ける」ではなく「踏ん張れる」ことです。
足幅・甲の高さ・アーチ形状と靴のラストが噛み合うと、母趾球と小趾球で床を“つかむ”感覚が得られ、重量が上がってもブレにくくなります。
痛みや痺れが出るモデルは、たとえ評判が良くてもあなたには合っていません。
クイック結論
| あなたの条件 | 最初の一足のヒール候補 |
|---|---|
| 背屈〜6cm ハイバー寄り | 高め 25〜22mm |
| 背屈7〜9cm(平均) ナロースタンス | 標準 20〜22mm |
| 背屈10cm〜(柔らかめ) ローバー×ワイドスタンス | 低め 15〜20mm |
迷ったら標準ヒール(20–22mm)から試し、次に足型と剛性で詰めていきましょう。
シューズ構造と仕様を理解する
ヒール高
- 低め:15〜16mm
→ローバー/ワイド向け、重心低めで安定 - 標準:20〜22mm
→汎用性が高い“まずはここ” - 高め:25mm前後
→背屈不足の補助が強く、フロント系やOH系も楽に
ヒールは高ければ良いわけではありません。高すぎると前足部に荷重が流れやすくなる人もいます。
自己診断(3章)と合わせて、姿勢が楽になるが前のめりにならない高さを探すのがコツです。
ヒール素材と踏み心地
| 素材 | 特徴 | 向き |
|---|---|---|
| TPU | 高剛性・軽量・耐久◎。踏み心地は硬めで反発が素直 | 迷ったらこれ(オールラウンド) |
| 木製 | 剛性は最高レベル。とても硬い踏み心地で“据わり”重視 | 競技志向・好みが合えば最強 |
| EVA等 | やや沈む・軽快。入門的で“硬すぎない” | 初心者/軽量志向/日常の兼用も視野 |
剛性が上がるほど「据わり(どっしり感)」は増しますが、足への当たりは強めになります。
木製ヒールはハマる人には最高ですが、硬さが苦手な人には疲れやすいことも。
TPUはバランス型で失敗が少ないです。
アッパー・ストラップ・ラスト
- アッパー:
合成繊維=軽量・通気
レザー=ホールド・耐久 - ストラップ:
1本=甲中心
2本=前足部+甲で微調整しやすい - トゥボックス:
ブランドごとのワイド/ナロー傾向に注意
ストラップ本数は「微調整の自由度」に直結します。足幅や甲高の差が大きい方ほど、2本ストラップが安心。
ラストはブランドで一貫傾向があるため、後で比較表(モデルごと)を見る前提で覚えておきましょう。
アウトソールとねじれ剛性
- グリップパターン:ラバー床/木床/ジムマットなど床材との相性が出る
- ねじれ剛性:使用重量が増すほど、足部の内外倒れを抑えたい
- 重量:軽さ=動きやすさ、重さ=据わり…のトレードオフ
スクワットなどで使用重量が伸びるほど、靴のねじれ剛性が効いてきます。軽量靴の“動きやすさ”は魅力ですが、高重量での据わりを優先するなら、やや重め・剛性高めが安心です。
失敗しない選び方(実践ガイド)
まずは“高さ×フォーム×足型”の3点で絞る
- 自己診断(3章)の結果をもとに、ヒール帯を1つに絞る
- 自分のスクワット様式(ハイバー/ローバー、スタンス幅)を再確認
- 足幅・甲高・アーチの傾向を最優先でフィルター
カタログをいきなり眺めると迷子になります。先に条件を決め打ちしてから候補を探すと、短時間で「合う可能性が高い靴」だけに出会えます。
足の測り方
- 足長:踵〜最長趾先(夕方計測推奨/左右差あり)
- 足幅:母趾球と小趾球の一番広い位置(左右とも)
- 換算:cm→US/EUはメーカーの表を必ず参照(同じUSでも実寸が違うことあり)
サイズはメーカーによって基準が異なるので、最後は各ブランドのサイズ表(実測値)で照合するのが鉄則です。US/EU表記は同じ数字でも実寸がズレることがあります。
必ず両足を測り、大きい方に合わせてください。履くときのソックス厚もトレーニング当日と揃えます。
また夕方は日中の生活で軽いむくみが生じ、足長・足幅・甲周りの体積が朝よりわずかに大きくなります。多くの人がトレーニングする時間帯に近い状態で測っておくと、実使用時にきつくなりにくいです。
試着チェックリスト
チェックリスト
- つま先余裕:爪1枚分前後
- 踵:浮かない・擦れない
- 甲:ストラップを締めても痛みゼロ〜小
- 母趾球・小趾球:床を“つかめる”感触が出るか
- 軽いスクワット姿勢:前足部に乗りすぎないか、ふらつかないか
「立ち姿の快適さ」より、しゃがんだ時の安定を優先して見ます。特に母趾球・小趾球で床を捉えられる感覚は、重量が上がるほど差になります。
選び方の指針
- 幅広かも?:いつもの靴で羽根(紐の両側パーツ)が大きく開いても当たって痛い、あるいは最初から広く開いていないと履けない
- 幅狭かも?:羽根が閉じきっても緩い(甲や前足部に余りが出る)
- 甲高かも?:通常の紐テンションで甲に食い込み跡・しびれが出る、面ファスやストラップ位置が甲に当たりやすい
- 甲低かも?:しっかり締めても甲が浮き、踵が抜けやすい(インソールで体積調整が有効)
幅広・甲高 → ワイドラストと調整幅の大きいストラップ(2本など)を優先。
幅狭・甲低 → 踵カップのホールドと甲周りの密着感が強いモデルが合いやすい。
土踏まずが敏感な人 → アーチサポートの当たり(インソール形状)が合うモデルを最優先。
ここでの役割は「自分の足のボリューム感を素早く把握すること」です。詳細な測定や数値化は「足の測り方」に任せ、ここではフィットの見極め方とモデル選びの方向性だけに絞っています。
競技・種目別ガイド
ウェイトリフティング(スナッチ/クリーン&ジャーク)
- 目安:標準〜高めのヒール(20〜25mm)× 高剛性、前足部は広めの接地面
- ねらい:受け(キャッチ)姿勢での前後バランス、立ち上がりでの力の直結、切り返し時のブレ抑制
- 試し方:フロントスクワットやオーバーヘッドスクワットを軽めの重量で行い、標準ヒールと高めヒールを動画で比較(側面・正面)
ウェイトリフティングは深い位置まで沈んで受け、そのまま立ち上がります。足首の背屈余裕が大きく求められるため、標準〜高めヒールだと姿勢が作りやすく、前傾過多も抑えやすいです。
剛性が高い靴は沈み込みが少なく、バーの揺れを拾いにくいので立ち上がりが安定します。
木床やプラットフォームでは、全面がしっかり接地するパターンのソールが相性良好です。
パワーリフティング(スクワット)
- ハイバー/ナロー寄り:標準〜高めヒールで上体を立てやすくする
- ローバー/ワイド寄り:低め〜フラットも有力。ねじれ剛性とアウトソールの広さを重視
- 迷ったら:まず標準ヒール(20〜22mm)から。動画で膝軌道(第2趾方向)と前傾度、ふくらはぎの張りをチェックし、1段階上下で調整
パワーリフティングは記録重量を扱うため「据わり」と再現性が最優先です。
ハイバーは膝関与が相対的に大きく、ヒールの補助が効きやすい一方、ローバー×ワイドは股関節主導で足首の要求が小さく、低め〜フラットでも安定しやすい傾向があります。
重量が伸びるほど、靴のねじれ剛性(内外への倒れ込みを抑える力)や、底面積の広いアウトソールが効いてきます。
デッドリフト
デッドリフトはリフティングシューズではなくフラットで薄底のシューズが基本です
- 原則:薄底・フラット(スリッパ/ゼロドロップ)
- 目的:可動域短縮+足圧の安定(特にスモウは横グリップが重要)
デッドリフトでは、スタート姿勢でいかにバーを早く動かせるかが鍵です。
薄底は足圧を低く広く分散でき、設置感が強いので引き始めで体が前に倒れにくくなります。
スモウデッドリフトでは外側へ押し広げる力に耐える必要があるため、横グリップと外周エッジの立ったソールが効きます。
コンベンショナルデッドリフトでも、薄底の方が骨盤をバックに引いたまま肩とバーの位置関係を整えやすいです。
そのためデッドリフト単体でのやりやすさを重視した場合、リフティングシューズは適さないことが多いです。
ベンチプレス
- 優先:床グリップ/滑りにくさ/踵の安定
- 備考:ヒールは必須ではありません(トレーニングシューズ等でも可)
ベンチは足で床を強く押せないとブリッジが崩れ、肩や背中のポジションが保てません。
選ぶ基準は「滑らないこと」と「踵が安定していること」。ソールはフラットで硬め、前足部の接地面が広いパターンが扱いやすいです。床との相性も重要なので、普段使うジム床で試すのが確実です。
ケース別トラブルシューティング
よくある症状と対策
| 症状 | ありがちな原因 | すぐできる対策 |
|---|---|---|
| 深くしゃがめない | 足関節背屈不足 ヒール低すぎ | ヒール1段UP つま先開きを+5〜10° |
| 体幹前傾が強い | 足関節背屈不足 癖 | ヒール1段UP フロントSQで矯正練習 |
| 膝が内に入る | 足部の倒れ込み 横剛性不足 | ストラップ強化 剛性の高いモデルへ |
| つま先が痛い | トゥボックスが狭い 甲圧 | ワイドラストへ 紐・面ファス再調整 |
| 踵が浮く・抜ける | ヒールカップ形状ミスマッチ | サイズ再検討 踵パッド追加 |
| 足裏が滑る | ソール汚れ 床との相性 | ソール清掃床拭き グリップ強靴へ |
| ふくらはぎ張る | ヒール高すぎ | 1段低いヒールへ変更 |
深くしゃがめない
原因
足首の背屈が不足すると、すねが前へ倒れ切れず、重心を保つために「かかとが浮く」「骨盤が後ろに丸まる(ボトムだけ腰が丸まる)」のどちらかが起きやすくなります。スタンスが狭すぎ/つま先が正面すぎでも、必要な背屈量が増えて沈みにくくなります。股関節の屈曲制限がある場合も底で止まりやすくなります。
見分け方
・壁つま先テストが短い/左右差が大きい
・最後の一瞬でかかとが浮く、またはボトムだけ腰が丸まる
対策
ヒールを1段上げる、つま先角度を5〜10°外へ開くと深さが出やすくなります。
底で腰が丸まる場合は重量を一段軽くし、可動域ドリル(カーフ・ソールアクティベーションなど)も併用。
体幹前傾が強い
原因
「すねが前へ出ない(背屈不足)」のまま重心を中足部に保とうとすると、体幹を前に倒して帳尻を合わせます。ローバーやワイドスタンスは意図的に前傾が増えますが、必要以上に前へ倒れるのは背屈不足や胸椎の伸展不足、腹圧(ブレーシング)不足が背景にあることが多いです。大腿骨が長い体型も前傾が出やすくなります。
見分け方(簡易)
・側面動画でバーがつま先側へ流れる
・すねが立ったまま、体幹だけ前に折れていく
対策
ハイバーやフロントスクワットで比較し、姿勢が立てやすいならヒール高の不足が疑われます。逆にヒールを上げても前足部に乗りすぎてバランスが崩れるなら、ヒールを一段下げて中足部に圧を戻すのが有効です。
膝が内に入る
原因
足部の内倒れ(アーチが潰れる=過回内)に連動して、脛・大腿が内旋し、膝がつま先より内側へ入りやすくなります。靴のねじれ剛性が低い/ストラップ固定が弱い/スタンスやつま先角が股関節の構造と合っていない、などでも起きます。負荷が高すぎて踏ん張り切れないときにも出やすい現象です。
見分け方(簡易)
・正面動画で膝がつま先ラインを越えて内側へ
・足裏の内側だけにシワや圧が偏る
対策
足裏の三点(母趾球・小趾球・踵)を意識し、前足部のストラップで横ブレを抑えると安定します。ねじれ剛性が低い靴は潰されやすいので、底面積が広くサイドの張り出しがあるモデルへ。負荷が高すぎる場合は重量を5〜10%落としてフォーム優先。
つま先が痛い
原因
トゥボックスが狭い、サイズが短い、または甲の締めすぎで中足部に圧が集中すると、母趾球〜指先に痛みが出ます。ヒールが高すぎて前足部に荷重が流れている場合や、厚いソックス/厚手インソールで“高さ”が足りなくなる場合も痛みの原因になります。
見分け方(簡易)
・立位では平気だが、しゃがむと先端が突っ張る
・紐を1段緩めると痛みが和らぐ(締め位置の問題)
対策
まず紐をつま先側だけ1段緩め、中足部〜甲で固定します。厚いソックスや厚手インソールが当たりを強めることもあるため、薄手に変更して確認。それでも痛むならワイドラストやトゥボックス高めのモデルが適します。
踵が浮く・抜ける
原因
サイズが長い/ヒールカップ形状が足と合っていない/甲の体積が小さく締めても押さえ込めない、などの“フィットの問題”と、底だけで起きる“可動域の問題(深くなると背屈不足で踵が持ち上がる)”に分かれます。
見分け方(簡易)
・立っただけで浮く→フィットの問題が濃厚
・浅い位置は大丈夫、底だけで浮く→可動域不足の可能性
対策
サイズ/形状のミスマッチと、足首の可動域不足が原因に分かれます。立位で踵が浮くならフィットの問題が濃厚。最上段の穴でヒールロックを使い、必要なら踵パッドで空間を埋めます。深い位置だけで浮くなら可動域不足の可能性があり、ヒールを上げるか可動域ドリルで改善を。
足裏が滑る
原因
摩擦は「素材×接地面積×間に挟まるもの(粉塵・汗・チョーク)」で決まります。靴底や床が汚れている/床材とトレッドの相性が悪い/ラバーが硬化・摩耗している、といった要因で一気に滑りやすくなります。湿度や汗膜も摩擦を大きく下げます。
見分け方(簡易)
・靴底と床を拭くと改善する→表面コンディションの問題
・いつも同じ床でだけ滑る→床×トレッドの相性問題
対策
ソールと床の清掃が最優先。粉塵・汗・チョークの薄膜だけで摩擦は大きく低下します。床材に合うトレッドへ変更(木床=全面接地・細溝、ラバー床=微細パターン+やや粘り)も検討。
ふくらはぎが張る
原因
ヒールが高すぎて前足部へ荷重が流れる、またはつま先で踏みすぎるフォームだと、足関節底屈(ふくらはぎ側)が働き過ぎて張りが出ます。背屈不足で“前に突っ込む”動きになっている場合や、急に剛性の高い靴へ替えて筋の伸張負荷が増えたときにも起こりやすいです。
見分け方(簡易)
・ヒールを一段下げると楽になる
・つま先角度を少し戻す/スタンスを狭めると張りが軽くなる
対策
ヒール過多で前足部に荷重が流れているサインのことがあります。ヒールを一段下げ、中足部に圧を戻すと緩みやすいです。ウォームアップでカーフの伸長と足首のモビリティを入れると持続が良くなります。
鋭い痛み、しびれ、関節の不安定感が続く場合は使用を中止し、医療・専門家に相談してください。フォームが乱れる重量でのテストは避け、同じセットアップ(ラック・床・重量)で比較することが、正しい判断への近道です。
微調整テクニック
- 紐とストラップは役割が違う:紐=甲全体、ストラップ=足のレバー固定
- スタンス幅・つま先角度:5°単位の微調整で荷重線が改善
- インソール:アーチの“当たり”が合うと、痛みが激減することがある
紐とストラップの使い分け
- 紐=足全体の体積を整える
つま先側はわずかに緩め、中足部〜甲中央に向かって段階的にタイトにすると、母趾球・小趾球に体重を乗せやすくなります。立位だけでなく、軽くしゃがんだ姿勢で当たりが出ないかも確認してください。 - ヒールロックで踵を座らせる
最上段の穴を使った走者結び(ヒールロック)にすると、踵の浮きや擦れが出にくくなります。まず紐で踵をロックし、その後にストラップで固定すると安定します。 - ストラップ=足のレバー固定
前足部のストラップは母趾球・小趾球付近を押さえて左右のブレを抑えます。
甲上のストラップは靴内の上下方向の遊びを減らし、足と靴の一体感を高めることで、踵がヒールカップに“座り”やすくなります。
二本ストラップのモデルでは、前足部=横ブレ抑制/甲上=ロックダウンという役割分担で使い分けると安定します。※締めすぎは痺れや痛みの原因になりますので、動作中に違和感が出ない最小限のテンションで調整してください。 - 締める場所は“最後の2穴だけ”など局所で
甲が高い方は上側が強いストラップのモデルだと楽なことが多いです。強く締めるのは必要最小限にして、痛みや痺れが出る前に微調整してください。
スタンス幅・つま先角度の微調整
- 調整は小刻みに(角度5度・幅は足半分)
つま先角度は5°刻み、スタンスは“自分の足幅の半分”刻みで広げたり狭めたりすると、体感と動画で差が分かりやすくなります。 - 正解の目安を持つ
しゃがんだ時に膝のお皿が第2趾の方向へ進み、土踏まずが潰れ過ぎず、母趾球・小趾球・踵の三点に圧が均等に残っていれば良好です。 - ニーインが出るときの処方
つま先角度を5°だけ外へ向ける、またはスタンスを足半分だけ広げると、膝の軌道が整いやすいです。前足部に乗りすぎるなら角度を5°戻すか、スタンスを少し狭めて中足部に圧を戻します。 - A/Bテストで確かめる
同じ重量で3レップずつ、側面と正面を動画撮影します。前傾が減り、立ち上がりで内外のブレが少ない方を採用すると失敗がありません。
インソールの活用
- 甲低で空間が余る→体積を足す
靴内に余裕がある場合は、薄めのボリュームアップ用インソール(2〜3mm)で体積を足すと甲の密着が高まります。踵の抜けも減りやすいです。 - アーチが敏感→“当たり”を和らげる
盛りが強すぎない平坦寄りのインソールに替えると、土踏まずの圧迫感が軽くなります。逆に土踏まずが潰れて痛い方は、低〜中程度のアーチサポートで“面”で支えるタイプを試してみてください。 - カットは少しずつ・動作で必ず確認
つま先側から数ミリずつトリミングします。入れ替え後は軽いスクワットで当たりや痺れの有無を必ず確認し、違和感があれば元に戻します。 - 効かないときはトゥボックスを見直す
インソールで改善しない痛みや不安定感は、サイズや足形の相性が原因のことがあります。モデル変更も視野に入れてください。
トラブル別の即効リカバリー
- 甲が痛い・しびれる
紐の中央2〜3列を1段だけゆるめて、圧の逃げ道を作ります。次に甲上ストラップを少し緩めます。必要に応じてベロの下に薄いタンパッドを入れると圧が分散しやすいです。これでも改善しない場合は、トゥボックスやサイズの相性を見直してください。 - 踵が抜ける
最上段でヒールロックを作り、踵に体重を乗せてからストラップで固定します。必要に応じて踵パッドで空間を埋めます。靴下を薄手に変えると改善する場合もあります。 - つま先が当たる
つま先側の紐を1段緩め、中足部〜甲で固定します。厚手ソックスや厚いインソールが原因なら薄手へ変更します。根本的にはワイドラストやトゥボックス高めのモデルが適します。 - 小趾側が痛い(外側の当たり)
つま先角度を5°だけ内側へ戻す、または前足部のストラップを1目盛り緩めます。アウトソール外周が強く当たる場合は、サイズやラストの再検討が有効です。

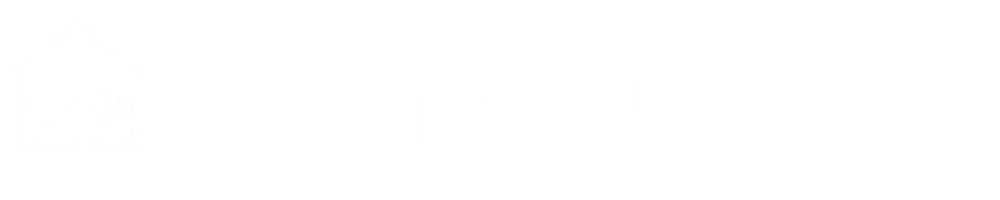


























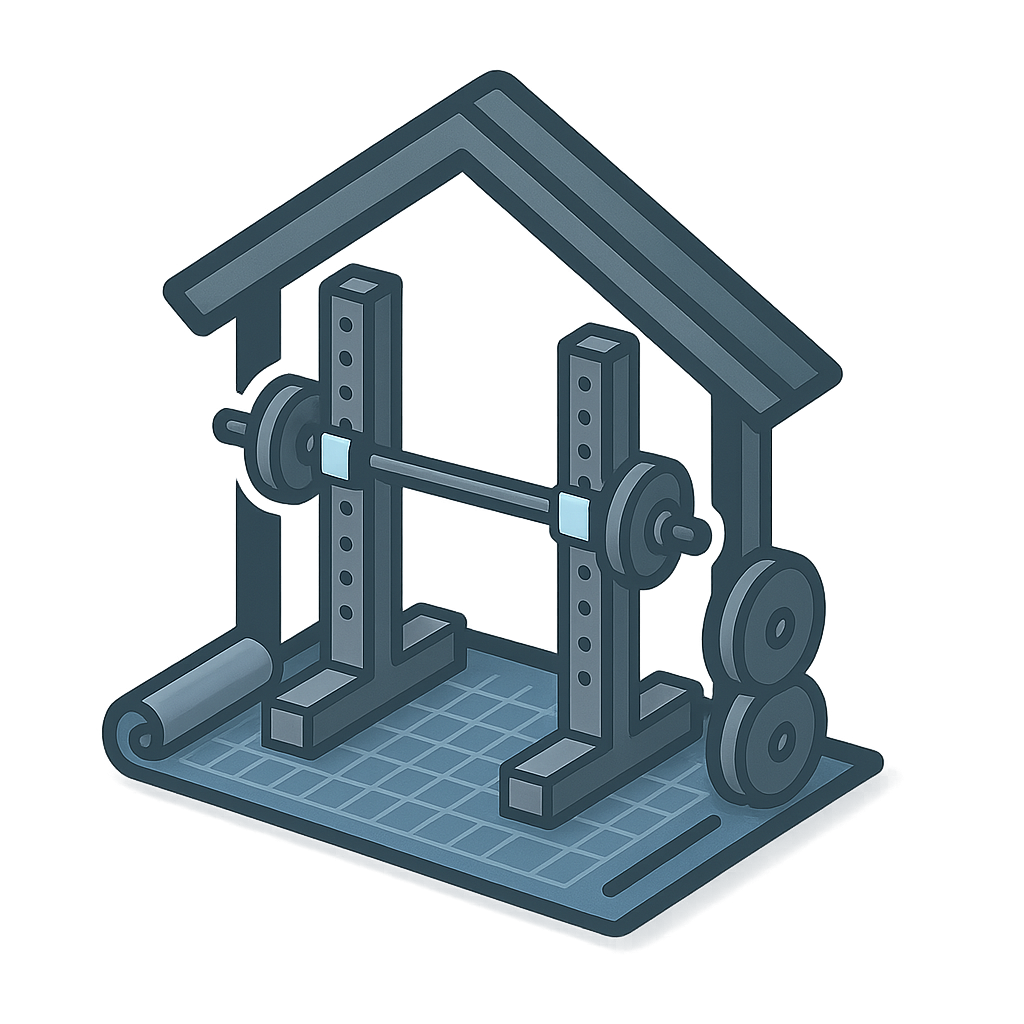


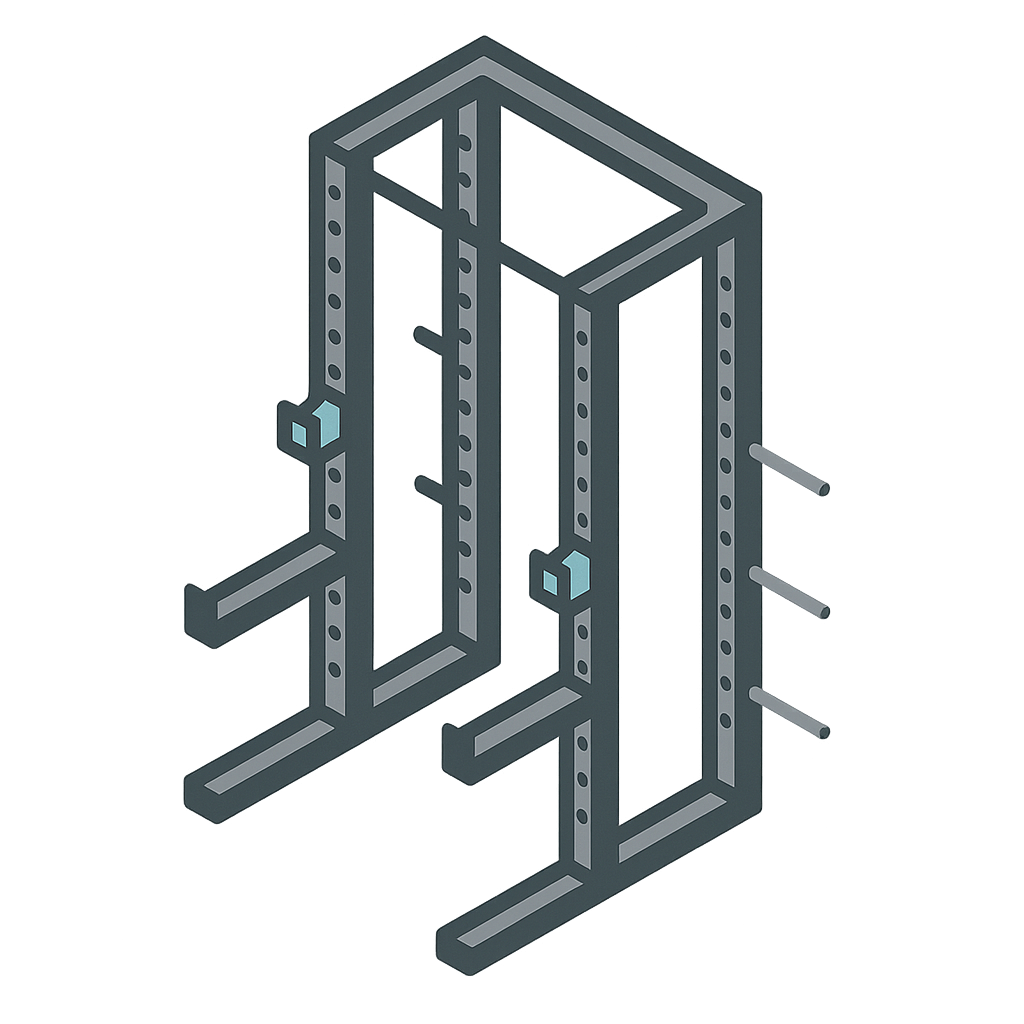
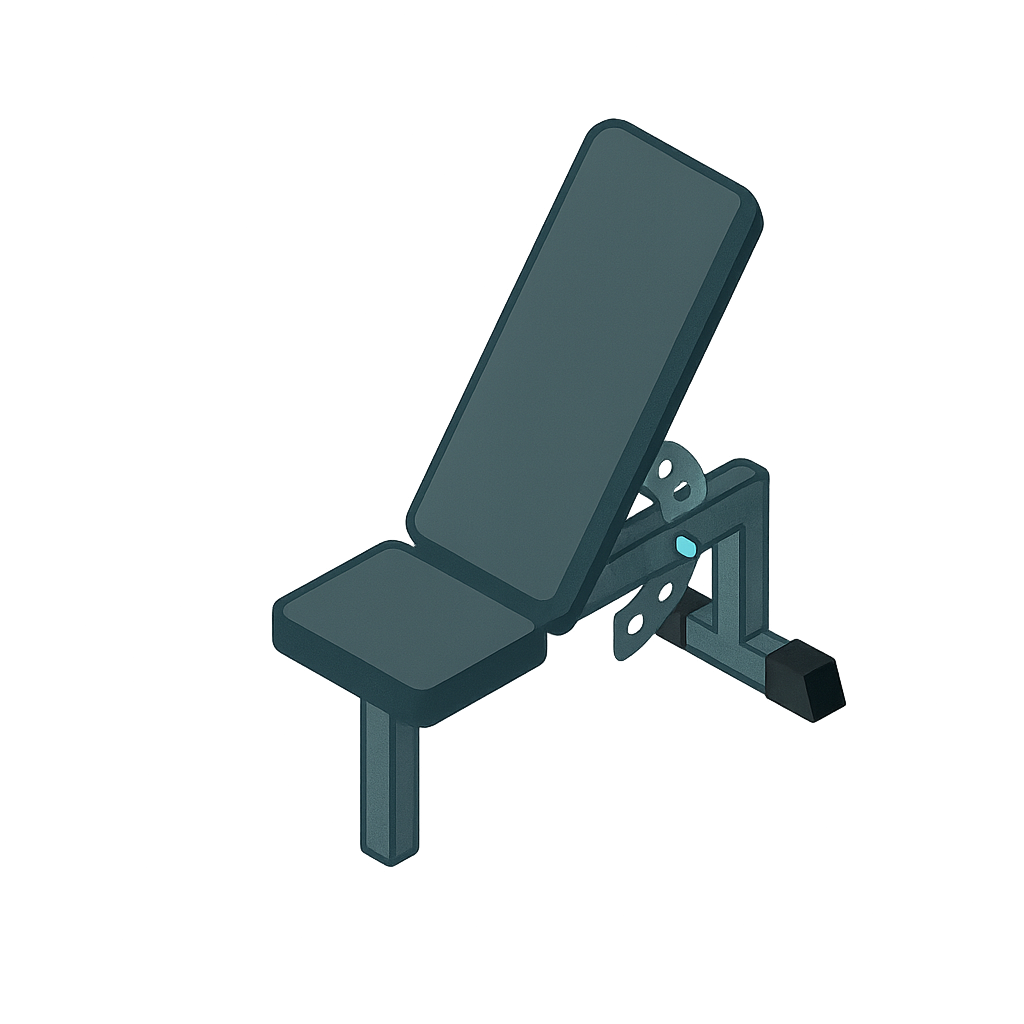
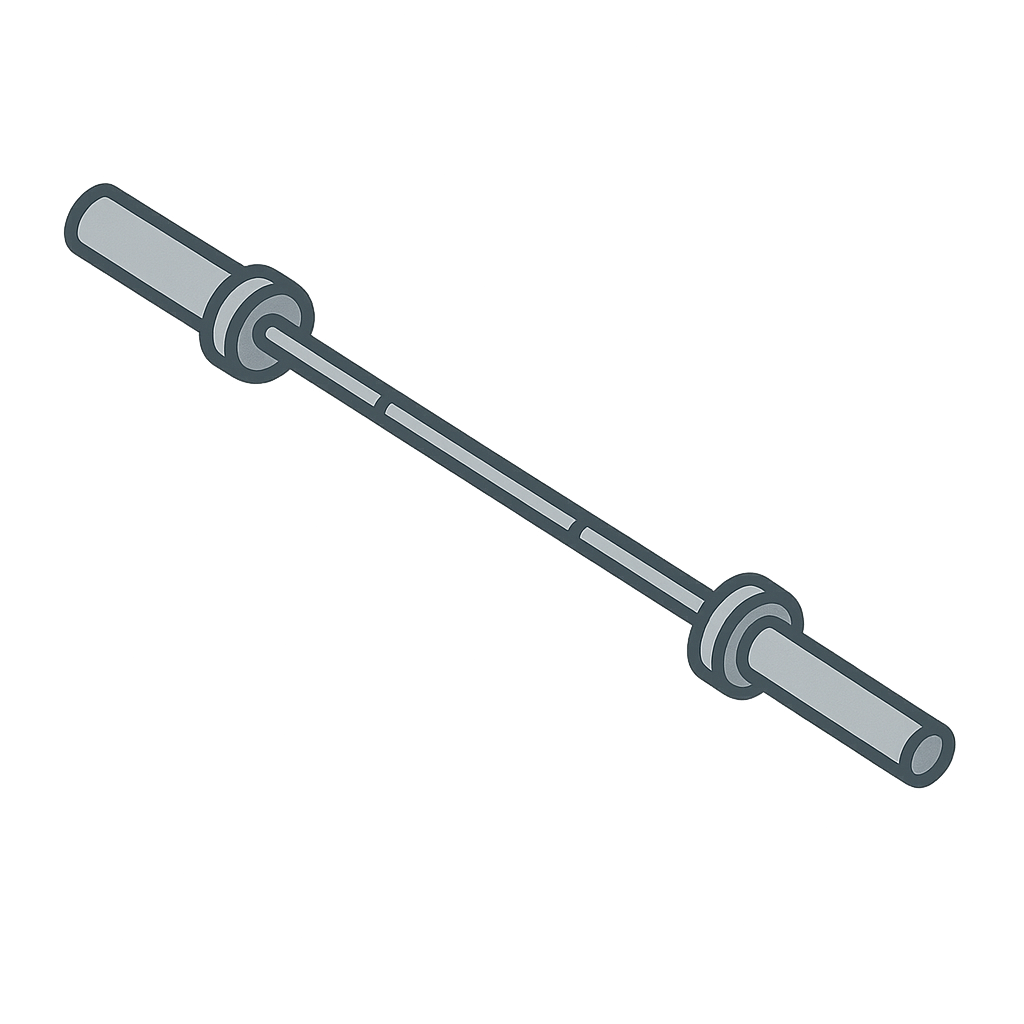
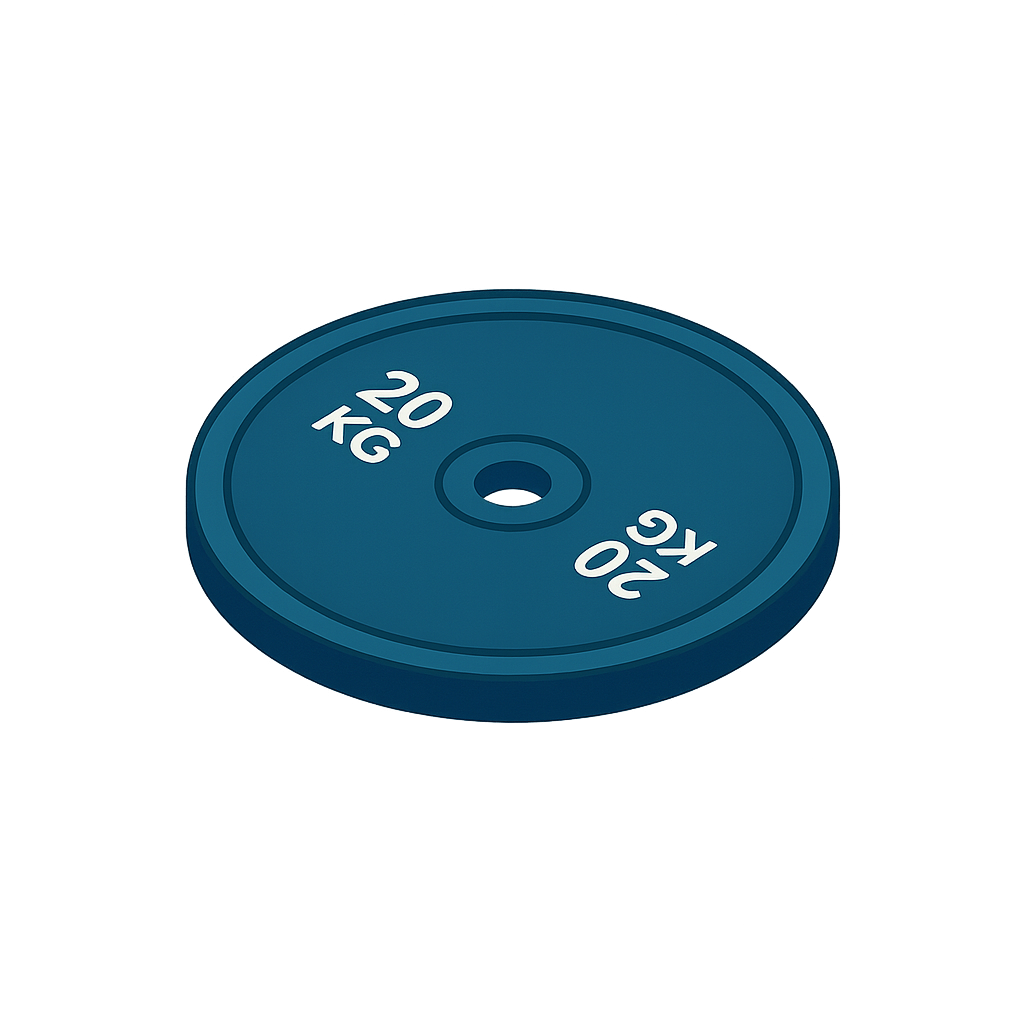
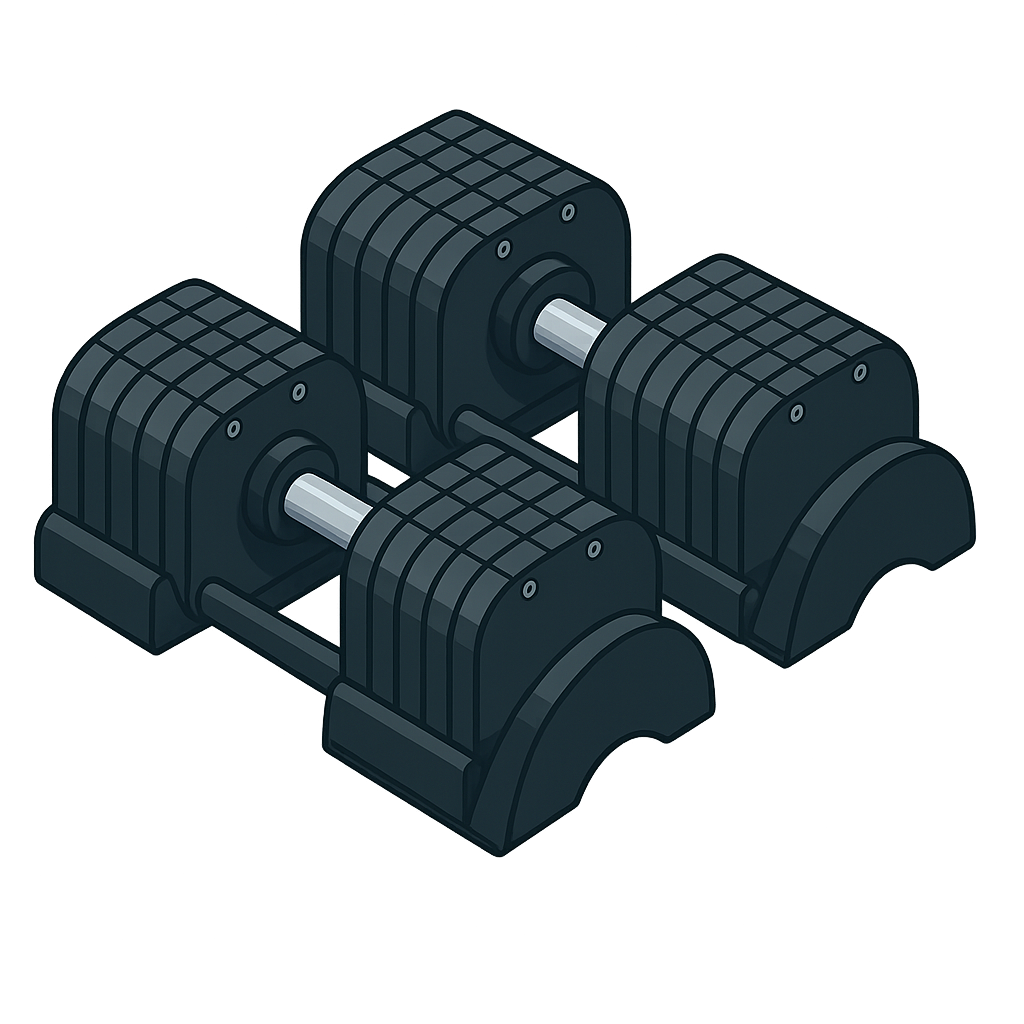






コメント